【農業の面白さはココにある!】農業が現代社会の構造の礎となっていた件[私が農業に興味を持った理由]
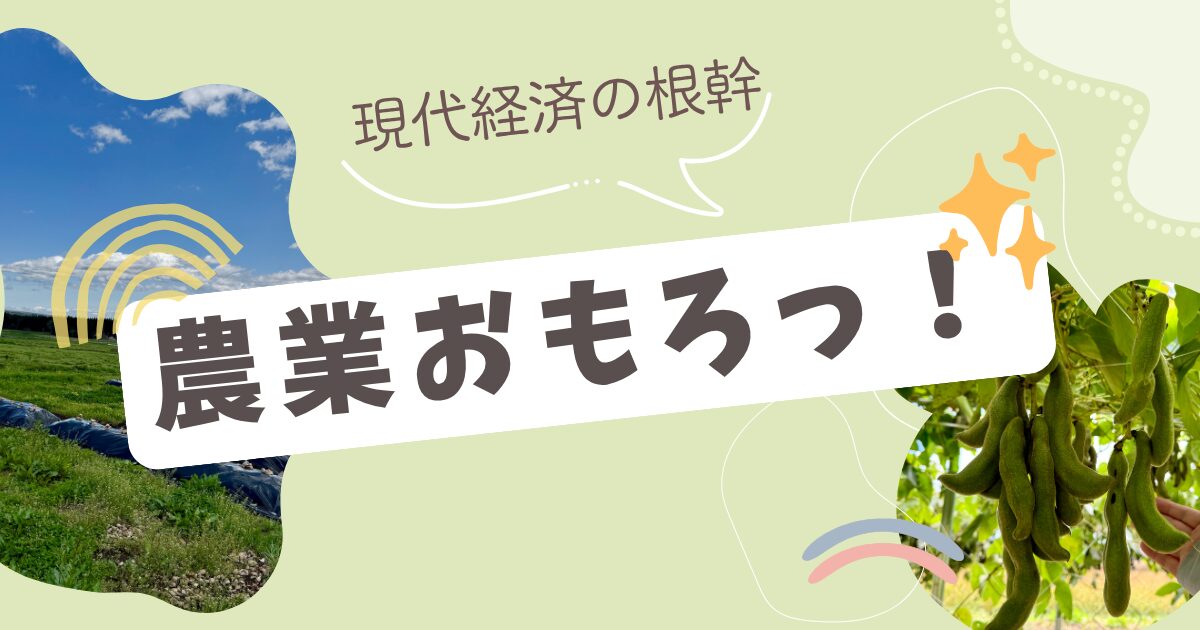
 あお
あお農業って実は現代社会の構造の礎になってるんだよ



それは「食」が人間にとって欠かせないものだってこと?



それもそうだし「経済」とか「労働」とか「戦争」とか人類社会の営みすべてに農業が影響してるの!
「食」と聞くとものすごく身近で大切なものとして実感する人は多いですよね。
ですが、その「食」を支える(というか根本)である「農業」となると、”どこか遠い国の話”ぐらいに思ってる人の方が多数派だと思います。



え?そんなことないよ!自分事として真剣にいつも考えてるよ!



えっ!もしかして何も知らずに生きてきたの私だけ…?



う、うそ嘘!



私も正直わからないことだらけだよ



よ、よかったぁ〜
実は私、田舎に移住して自分で家庭菜園を始めるまでは、米や野菜などの作物がどのようにして育てられているか知りもしなかったし、ましてや「農業について」なんて考えたことなんてありませんでした。
でも少し調べてみると、冷や汗が出るほど恐怖を感じたんです、「農業」のヤバさに…!



後継者不足とか農業従事者が激減してるって話!?



そういう現代社会の問題だけじゃなくて、色んな意味でヤバいの!!
この記事では、農業が現代社会の礎となった背景や、功罪のヤバさについて紹介します。
「農業」を身近に感じたこともない人でも「マジかぁ!?」と興味惹かれること必至ですよー!!
狩猟採集から農耕へ
これは普通に社会科の授業などで習う話ですが、
約1万2000年前、氷河期が終わりを告げ、地球の気候が温暖になり始めた頃、人類は大きな転換点を迎えました。
それまで何十万年も続いた狩猟採集の生活から、植物を育て、動物を飼いならす「農耕」という新しい技術が発明されたんです。



日本でいうと縄文時代の後期から弥生時代の初期ぐらいの話だよ
農耕がはじまる前の狩猟採集社会では、食料を求めて常に移動する必要がありましたが、、、
ある日、食べ残した種から偶然に植物が生えてくるのを目撃した人類のご祖先様たちは、



もしかして食べ物って自分たちの手でも作れんじゃない!?
革命的な発想に至ったと考えられています。
農耕の起源とされる中東の「肥沃な三日月地帯」と呼ばれる地域には、もともと野生の小麦や大麦が豊富だったことが幸いしたようです。
人々は徐々に、これらの植物の栽培方法を学んでいきました。
ほぼ同時期に、ヤギや羊などの動物の家畜の飼育も始まったようです。



農業が始まった結果、人が定住して文明が発達していったよ



歴史の授業の最初の方で習ったね
人や動物が増えると、生き物の糞尿も増えていきました。
その糞尿をまとめて捨てていた肥溜めから植物が成長しているのを発見して、



💩って作物の生育にうってつけじゃね!?
と、「堆肥」のような概念の発見もあったようです。
ただしこの時点では、生業としての「農業」というよりも、皆で協力し合いながら行う「農耕」と言った方が適切かもしれません。
農業が広まった理由:狩猟採集より「良くなった点」「悪くなった点」
農耕という新しい技術は、約1万年かけて世界中に広がっていきました。
(そもそも)農耕が必要とされた理由



でもさ、偶発的とはいえ、なんで農耕やろうと思ったんだろ?



それには色んな事情が絡み合って「そうせざるをえなかった」みたいだよ
- 人口が増えてしまった
狩猟採集では支えられる人口に限界があった - 狩猟採集は不確定要素が多い
いつも安定して食料が手に入るとは限らないし、同じ場所で得られる食料は限られていた(食い尽くしたら移動しなければならないから定住できなかった) - 気候変動への適応
それまでの狩猟対象だった大型動物が減少してしまった - 定住生活という魅力
乳幼児や高齢者にとって、常に移動する生活は厳しかった
こうした不安定な暮らしを抜け出すために、人類は「食べ物を自分たちで育てる」という挑戦に挑んだと考えられています。
つまり農耕は「より安定した暮らし」を求める人間の願望から生まれた、生存のための大きな発明だったのです!



現代の私達も本能的に「安定した生活」を求めてしまう理由が分かる気がするよね



「安定」は人類のDNAに刻み込まれてるのかもね
農業が広まって良くなった点
農耕の技術が発展していく過程で、役割の分担(分業)という概念が生まれていきました。
その結果、確立されたのが、農耕を生業とする「農業」という職業です。
農業が広まることによって、良くなった点がいくつもあります。
農業によって良くなった点
- 食料を計画的かつ安定的に確保できる
毎日山を歩き回らなくても畑さえあれば生きていけるようになった - 定住生活ができるようになった
農業が始まったことで村や町ができ、家を持つ暮らしが広がった - 余剰生産が可能になった
食べ物を「余らせる」ことができるようになり、それが物々交換や市場経済の基盤となった - 専門技術の発達
食料生産に携わらない人々が生まれることにより、道具制作や芸術など「生存に直接関わらない」専門的分野が発展した



「経済」という概念が生まれたのも農業がキッカケだよ



「余った食料」を交換して助け合ったのがスタートなんだね



それもそうだし「自分の時間」を切り売りする「労働」という概念が生まれたのも農業がキッカケなの。小作人とかね



土地を借りて作物を育てる人のことだね



安定して栽培するための天候を読む技術が天文学の発展につながったし、農耕のための灌漑システムが工学の礎になったとも言われてるんだよ



すべての道は農業に通じていたのかっ!?
そう考えると、農業の威力ってヤバいですよね!!
農業の罠!?罪!?悪くなった点
良くなった点が多々ある反面、農業への移行は必ずしも生活の”向上”ではなかったとも言われています。
農業によって悪くなった点
- 労働時間の増加
狩猟採集民は1日あたり3~5時間の労働で十分な食料を得られたが、農民は日の出から日没まで働く必要があった - 食事の質の低下
主食が特定の作物に依存するようになり、栄養バランスが悪化した。実際、農耕民の骨は狩猟採集民より背が低く、栄養不良の痕跡が見られる - 疫病の増加
定住と人口密度の上昇に加え栄養バランスの悪化が免疫力の低下につながり、感染症が広がりやすくなった - 「格差社会」が生まれた
余剰食料を管理する権力者が生まれ、階級社会の基盤が形成された - 土地や作物をめぐる争いに発展
豊かな土地とそうでない土地で差が広がり、村(集団)同士で奪い合うようになった - 自然災害や天候による影響の拡大
作物に頼る生活のほうが、干ばつや洪水など自然災害や天候の影響を受けやすくなった - 環境問題の発生
森林伐採による土壌侵食、灌漑による塩害、モノカルチャー(単一作物栽培)による生物多様性の毀損など、新たな問題が生まれた
つまり農業は人間に「安定」と「発展」をもたらした一方で、「リスク」と「争いの種」も同時に抱え込んだんです。



日本で言えば弥生時代に入って身分という概念が出来たよね



たしか稲作の水耕栽培によって格差が生まれたって習ったね



格差はやがて戦争の原因にも発展していったよ
私(筆者)が特に衝撃を受けたのが、近代に生まれた化学肥料の生産技術の軍事利用です。
空気中の窒素を固定して化成肥料にする技術「ハーバー・ボッシュ法」は、当時の深刻な食糧問題を解決する画期的な発明だったのですが、、、
第一次世界大戦においては、爆薬の大量生産に応用されてしまったんです。



肥料作ってた工場で爆発事故が起きちゃって「これ爆薬になるんだ!」ってなったらしい



えっ!偶然の事故で発見されたってこと?



「育てる技術」で人口が爆発的に増えて、その同じ技術が「殺す技術」になって文字通り爆発しちゃったなんて、こんな皮肉ある!?!?



なんて人類って愚かなんだろう!
現代においては、軍事目的で発明された技術が私達の日常生活に欠かせない物になっている事例には、枚挙にいとまがありません。
たとえばGPSとかインターネットとかね。
なので、化成肥料が悪だとは一概に言えないのですが、複雑な気持ちになりますよね…。



発明した本人やその家族の末路を知ると、なおさら責める気にはなれないけどね…



悪いのは発明品や発明者ではなく戦争で悪用した人だもんね
農業は現代の経済の根幹である!
まぁ悲しいお知らせはこのぐらいにしておいて、農業がいかに我々が暮らす現代社会の根幹となっているか、あらためてまとめてみましょう。
農業の「余剰生産」が、現代の「資本蓄積」になった
→ 食料が余ったことで、他の人が別の仕事をできるようになった(職業分化・投資の発想)
農業の「土地所有」が、現代の「不動産」や「資産」になった
→ 土地を誰が所有するかが、社会的地位や富を決定する構造に



現代でも不動産や株とかの資産を持ってる人が強者だよね



『金持ち父さん』も「労働者ではなく資本家になれ」って言ってるもんね
農業の「収穫に応じた分配」が、現代の「労働に応じた報酬」になった
→ 成果に対して対価が支払われるという経済モデルの原型
農業の「租税制度」が、現代の「所得税・法人税」などの税金になった
→ 収穫量に応じて年貢を納める制度は、現代の課税システムと構造が同じ



「年貢の納め時だぁ!」ってやつだね



昔も今も税金はツライね
農業の「共同労働」が、現代の「会社組織」になった
→ 一人で成り立たない仕事を分業と協業で行う構造の出発点
農業の「備蓄」が、現代の「資産運用・投資」になった
→ 未来の飢饉に備えて保存する行動は、利益を見越した先行投資の思考につながる
農業の「時間管理(種まき・収穫)」が、現代の「スケジュール管理」になった
→ 自然のリズムに沿って仕事を進める意識が、計画性と納期厳守の習慣に似ている



どうやってリスクに備えたり助け合って支え合えばいいのか、農業を通して学んでいってる感じだよね



環境が厳しい地域に住んでる人たちほど計画的だという都市伝説はあながち間違いじゃないのかもね
農業の「交換経済(物々交換)」が、現代の「通貨経済」になった
→ 作物を交換する中で貨幣が生まれ、信用と流通が可能になった
農業の「労働力(小作制度)」が、現代の「雇用と労働市場」になった
→ 誰が何の仕事をどれだけするか、報酬はいくらか、という契約労働の始まり



農業が機械化されて収量が安定的に増産可能になると、不要となった労働力が都会の工場に流れていったという歴史もあるよ



そっか!産業革命が起きて労働市場が農地から移動したんだね
まとめ:農業という我らのルーツは功罪で溢れているからこそ面白い!
現代の日本は、ある程度まっとうな生活を送っていれば食に困らない豊かな国ですよね。
特に都会で生活していると、毎日「食べる」という行為をしているのにも関わらず、農業はどうしても「自分には関係ない世界」のように感じてしまっていました。
ですが私たちの働き方や経済の仕組み、社会的な格差の始まりなどルーツをたどってみたら、ほとんど農業に行き着くんです。



とりあえず「古代も現代も、人間がやることって何万年たっても変わらないのね」って思ったよ



確かに。古代からずっと食って働いて争ってるね
結局ところ、人類は「進化」なんてしていない。
厭世的な言い方かもしれませんが「ホモ・サピエンスなんて永遠にホモ・サピエンス」。
スマホを持とうが宇宙に行こうが、「ちょっと賢い猿」なんだなぁ、と。
今や人類にとって最大の武器であった(であろう)想像(創造)力もAI様に明け渡そうとしているし。
「何やってんだ我々は???」って呆れ返ってたら、自分でクワ握って畑耕してました。



…ん?そこの発想のジャンプがよく分からないんだけど?



失望の果には原点回帰しかなかったってことだよ
いやぁもぉ、「逆に面白い!」ってなったんですよ。
何をどう小難しく言おうと、要するに我々は食うことでしか生存できないわけで。
だからこそ、古代人も現代人もやることが同じなわけで。
だから、私は自分で畑を耕して、食料を自分で生産してみようと思ったんです。



ただし労働を切り売りするのではなく自分の畑で自発的にやってみたかったの



だから「就農」じゃなくて「起農」なのね
この話を聞いて、同じように農業を始めたいと思った人はいないかもしれませんが、ちょっとでも「へぇ!」と思っていただけたなら嬉しいです!



お気軽にコメントください♪